プロバイダー変更に伴い、ルーターとかの機器も取り換えたもののやっぱり繋がりませんでした。
昨日一日は何をやっても繋がらす、今日もセンターのお姉さんが電話越しの指導の元色々やったものの結局ダメ。しかしその後何とか繋がるようになりました。トラップ解除のごとく手順を踏まなければなりませんが。
ウチにはパソコンが複数台あって、今使ってるほうは有線で(結局また無線でなくなった)隣の弟は専用機械で無線で飛ばしてるんですが私のパソ子で繋げる場合、この専用機械と通信できる本体(?)を繋げているコードを何回か抜き差しすると繋がります。で、隣のパソ野郎を繋げる場合にはこの専用機械の電源コードを一回抜いて再度電源を入れると繋がります。ね、まさに爆弾解除さながらでしょ。
しかも一回パソ子の電源を切る度に繋がらなくなるので、この作業を毎回せなあかんという事態になったわけです。その上電話とコードで繋いでないといけないため、リビングにあった親機が私の部屋に来ました(爆)リビングに持って行っても電話が繋がらないようなので、いろんな意味で死活問題なため仕方なく置いてます。
未だかつてない状況です。一体どんな配線でこのマンションを建てたのか聞いてみたいです。電話線の位置は微妙だわ電波が来るところと来ないところがあるとか。他の部屋は分からんけど少なともこの部屋を売りに出す場合、こういう説明してないといかんですな。毎回売って下さいのチラシを入れてる業者がそれをやってるかは知りませんが。
では引き続き束帯の最後をやります。放置気味でゴメンナサイ(滝汗)
あと拍手ありがとうございます。こちらも近々差し替えるつもりです。
昨日一日は何をやっても繋がらす、今日もセンターのお姉さんが電話越しの指導の元色々やったものの結局ダメ。しかしその後何とか繋がるようになりました。トラップ解除のごとく手順を踏まなければなりませんが。
ウチにはパソコンが複数台あって、今使ってるほうは有線で(結局また無線でなくなった)隣の弟は専用機械で無線で飛ばしてるんですが私のパソ子で繋げる場合、この専用機械と通信できる本体(?)を繋げているコードを何回か抜き差しすると繋がります。で、隣のパソ野郎を繋げる場合にはこの専用機械の電源コードを一回抜いて再度電源を入れると繋がります。ね、まさに爆弾解除さながらでしょ。
しかも一回パソ子の電源を切る度に繋がらなくなるので、この作業を毎回せなあかんという事態になったわけです。その上電話とコードで繋いでないといけないため、リビングにあった親機が私の部屋に来ました(爆)リビングに持って行っても電話が繋がらないようなので、いろんな意味で死活問題なため仕方なく置いてます。
未だかつてない状況です。一体どんな配線でこのマンションを建てたのか聞いてみたいです。電話線の位置は微妙だわ電波が来るところと来ないところがあるとか。他の部屋は分からんけど少なともこの部屋を売りに出す場合、こういう説明してないといかんですな。毎回売って下さいのチラシを入れてる業者がそれをやってるかは知りませんが。
では引き続き束帯の最後をやります。放置気味でゴメンナサイ(滝汗)
あと拍手ありがとうございます。こちらも近々差し替えるつもりです。
PR
実資たんを業界用語風に言うとこう、か?四文字だから何となくゴロが悪いですが。こういう会話が一番合いそうなのって斉信な気がする。公任は似合わないよなぁ。
明日は部屋の片付けです。片付けできるんですが一週間かそこらすると元通りというありさまで。いい加減物もたくさん処分せねばならんのですがねぇ。漫画はちょくちょくアキバのなんとかオフで売りさばいてます。未だにコピーしたものが整理できてないのが大問題です。これの容量が多分一番多いと思うので。
残りの束帯の部分は明日上げます。もう少々お待ちを。
明日は部屋の片付けです。片付けできるんですが一週間かそこらすると元通りというありさまで。いい加減物もたくさん処分せねばならんのですがねぇ。漫画はちょくちょくアキバのなんとかオフで売りさばいてます。未だにコピーしたものが整理できてないのが大問題です。これの容量が多分一番多いと思うので。
残りの束帯の部分は明日上げます。もう少々お待ちを。
中川のおっさんの酔いどれ具合を見てたらふわっと佐理とか誠信が浮かびました。弱いくせに(多分)飲まずにはいられないのか。残ってるのはオモシロ話が多いから良いけど(鬼)
昨日束帯上げましたが、あれだけで2時間はくだらないです。その大半が変換とか。登録してるのにできないとか何様のつもりなんだい、と突っ込みしながら。ただでさえ歴史用語とか打つの面倒なのに。
何かあれだよね、落ちた自分が言うとマジ愚痴というか文句のようになるけども、会社の選考て都合良いよね。日程も全部こっちが合わせて、求められる受け答えとかしてさ。そもそもこういうことやってる時点で「普段通りの自分」とか絶対無理だし。その上求める人材像はどう見ても行成。人当たりがよくて、元気な人で、仕事ができる(これ重要)
思うにどんだけ人が良くても仕事ができなきゃだめなのにことさらに「人柄」を強調するのはどうかと。そりゃ性格悪いよりはマシですが公任とあきみっちゃんなら絶対誰でも公任取るっしょ。例えどんなに彼のプライドが高くて何かにつけて面倒臭い性格でも(酷)もっと極端に言えばムネ様と兼実だったらまあ兼実だと思うし。
世の中そんな人間がどれだけいると思ってるんだか。みんながみんな行成みたいだったら日本はもうとっくに良い方向に行っているはずです。
とはいえどんなに行成でも向こうが一方的に解雇通知とか送ってきたらどうしようもないわけですが。今まさにその状況。就職支援の人とか「会社の都合に合わせて」て大体口をそろえて言うけどいきなり解雇まで都合に合わせる義理なんかないって話ですよ。受けるほうだってそれなりの時間と労力を注いだわけなんですから。
と、くどくど言ってはみましたがさくっとスルーして下さい。最初の佐理とかの件だけ残ってればいいから(良くない)
昨日束帯上げましたが、あれだけで2時間はくだらないです。その大半が変換とか。登録してるのにできないとか何様のつもりなんだい、と突っ込みしながら。ただでさえ歴史用語とか打つの面倒なのに。
何かあれだよね、落ちた自分が言うとマジ愚痴というか文句のようになるけども、会社の選考て都合良いよね。日程も全部こっちが合わせて、求められる受け答えとかしてさ。そもそもこういうことやってる時点で「普段通りの自分」とか絶対無理だし。その上求める人材像はどう見ても行成。人当たりがよくて、元気な人で、仕事ができる(これ重要)
思うにどんだけ人が良くても仕事ができなきゃだめなのにことさらに「人柄」を強調するのはどうかと。そりゃ性格悪いよりはマシですが公任とあきみっちゃんなら絶対誰でも公任取るっしょ。例えどんなに彼のプライドが高くて何かにつけて面倒臭い性格でも(酷)もっと極端に言えばムネ様と兼実だったらまあ兼実だと思うし。
世の中そんな人間がどれだけいると思ってるんだか。みんながみんな行成みたいだったら日本はもうとっくに良い方向に行っているはずです。
とはいえどんなに行成でも向こうが一方的に解雇通知とか送ってきたらどうしようもないわけですが。今まさにその状況。就職支援の人とか「会社の都合に合わせて」て大体口をそろえて言うけどいきなり解雇まで都合に合わせる義理なんかないって話ですよ。受けるほうだってそれなりの時間と労力を注いだわけなんですから。
と、くどくど言ってはみましたがさくっとスルーして下さい。最初の佐理とかの件だけ残ってればいいから(良くない)
公任:
さて前回から少し間があったが、いよいよ束帯の着用順について説明したいと思う。なお細かいところを端折っている部分もあるかも知れないがそこはご容赦願いたい。
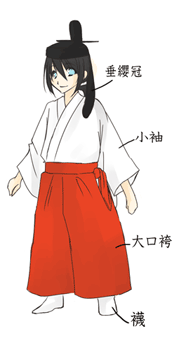 まずは「垂纓冠」をかぶり、上半身に「小袖」下半身に「大口袴」を着用する。足には「襪」。これが束帯の最下層の衣服になる。肩に垂れているの部分を「纓」と言うからこの名がついたわけだ。五位以上は「皀羅頭巾(くりのらのときん)」六位以下は「皀縵頭巾(くりのかとりのときん)」と定められている。皀とは黒色のことで羅、縵は素材名を指している。どちらも薄い生地で、違いは模様があるかどうかで前者には模様があるが後者にはそれがない。まあ後には上下関係なく模様がついたものを使用することになったがな。
まずは「垂纓冠」をかぶり、上半身に「小袖」下半身に「大口袴」を着用する。足には「襪」。これが束帯の最下層の衣服になる。肩に垂れているの部分を「纓」と言うからこの名がついたわけだ。五位以上は「皀羅頭巾(くりのらのときん)」六位以下は「皀縵頭巾(くりのかとりのときん)」と定められている。皀とは黒色のことで羅、縵は素材名を指している。どちらも薄い生地で、違いは模様があるかどうかで前者には模様があるが後者にはそれがない。まあ後には上下関係なく模様がついたものを使用することになったがな。
次に上半身の「小袖」だが、これが紹介されているのは「礼服」の部分で束帯のところで紹介しているものはない。手元の一冊の本に載っていたので一応描いてはみたが・・・。説明自体も多くないので何とも判断しかねるものでもあるな。
下半身の「大口袴」は裾を括っていないからその名がつき、夏冬に関係なく色はくれないと決まっていた。だから「赤大口」とも呼ばれていた。ただ若年は濃色であり、特殊な例として一日晴れの白装束の時には白を用いることもあった。
最後に「襪」だがこれは現在の靴下と同じで足袋のように親指のところで分かれていない。基本的に束帯以外の時は着用しないのが普通だった。
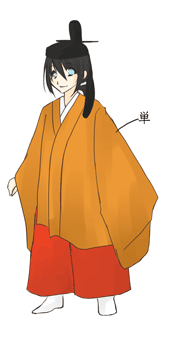 で、次に「単」を着る。この単は裏地がなく、多くの場合これが上半身の最下層となっている。色は基本的に紅で、素材は綾、模様は横繁菱(まあ普通の菱形が並んでいる状態だな)となり、天皇から六位の者まで共通だった。
で、次に「単」を着る。この単は裏地がなく、多くの場合これが上半身の最下層となっている。色は基本的に紅で、素材は綾、模様は横繁菱(まあ普通の菱形が並んでいる状態だな)となり、天皇から六位の者まで共通だった。
この単は狩衣の時などにも着用されたから、その時は束帯の時よりは多少派手になることが多かった。ちなみに今回の絵で色がオレンジぽくなっているが、これは次に着用する「衵」も同じ紅色であるから、わかりやすくするためにあえて変えたわけだ。間違えたわけではないぞ。そしてこの時足元には表袴も用意してある状態になっている。
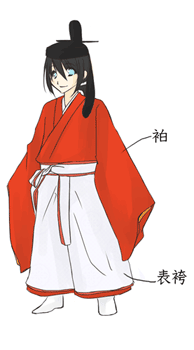 そしてこれが「衵」と「表袴」を着用した状態だ。衵は上記のように色は紅が普通だった。これは裏地も同じ紅だったぞ。素材は表が綾、裏が平絹。模様は表のみで小葵を使用していた。が、これは天皇および公卿の場合で、殿上人は模様なし。色も細かいことを言えば壮年は萌黄などの薄い色、それより年上は白が普通だった。実資とかな(笑)
そしてこれが「衵」と「表袴」を着用した状態だ。衵は上記のように色は紅が普通だった。これは裏地も同じ紅だったぞ。素材は表が綾、裏が平絹。模様は表のみで小葵を使用していた。が、これは天皇および公卿の場合で、殿上人は模様なし。色も細かいことを言えば壮年は萌黄などの薄い色、それより年上は白が普通だった。実資とかな(笑)
ちなみにこれの上にさらに「半臂(はんぴ)」というものを着用していたのだが、俺たちの時代、つまり平安中期頃には冬の束帯の場合、外から見えないこともあってほとんど省略されてしまっていた。必ず着用していたのは武官の闕腋袍と、夏の縫腋袍の時だった。なのでここでの説明はさくっと省かせてもらいたい。
下半身の「表袴」だが、はっきり言って複雑な構造をしているため絵を見てもいまいち理解できかねるので(爆)説明は簡単に。
色は夏冬関係なく表が白で裏が紅。この絵だと分かりにくが裏地が少しばかり長めになっているので、裾からすこしだけ紅の生地が覗いている。つまり三枚ずれて重なっているように見えるのだが、色が似たような感じだから遠目では判断しづらい。もともとは質素なものだったが延喜以降から模様付きのものなどが登場しはじめた。模様については簡単にまとめると下記のようになる。
公卿および禁色を許された蔵人 藤丸
(若年の場合は、窠に霰(かにあられ))
老年 八藤丸
殿上人以下は模様はなく、代わりに光沢を出したりしていたぞ。
表袴は袴というよりもズボンに似たような形をしている。まあその辺りは参考資料などを見てほしい。こればかりで申し訳ない。
 そして「下襲」を着用する。後ろに長く引いている部分を「裾(きょ)」といい、この長さは身分によって決まっていた。一時朱雀天皇の時はこの部分をやたら長くする者がかなりいたため、規制する事態にまでなった。その長さは親王が一尺五寸、大臣が一尺、納言が八寸、参議が六寸と定められた。一寸が約3.03センチで一尺はそれの10倍だから計算はまあ、自分で(逃げた)
そして「下襲」を着用する。後ろに長く引いている部分を「裾(きょ)」といい、この長さは身分によって決まっていた。一時朱雀天皇の時はこの部分をやたら長くする者がかなりいたため、規制する事態にまでなった。その長さは親王が一尺五寸、大臣が一尺、納言が八寸、参議が六寸と定められた。一寸が約3.03センチで一尺はそれの10倍だから計算はまあ、自分で(逃げた)
これが後三条天皇の時代になると大臣が七尺、大中納言が六尺、参議と散三位が五尺、四位五位が四尺というように延長され、この長さが写真などでよく見る長さとなったわけだ。大体2,3メートルくらいだな。
 こういう風景を見たことがあるだろうか。廊下で待機する場合などはこのように長い裾を手すりにかけていた。また例えば行成のようによく動く貴族の場合、長い裾が邪魔になるから、この部分を石帯や太刀にかけて移動していたぞ。
こういう風景を見たことがあるだろうか。廊下で待機する場合などはこのように長い裾を手すりにかけていた。また例えば行成のようによく動く貴族の場合、長い裾が邪魔になるから、この部分を石帯や太刀にかけて移動していたぞ。
色目と模様はいずれの場合も表が白で、裏地は天皇が濃蘇芳、公卿殿上人は黒もしくは濃蘇芳。模様は天皇が小葵、公卿が浮線綾、殿上人はなかった(裏地もあるが省略)
そしてこの下襲は正式な儀式以外、例えば天皇の行幸など一日限りの行事などの場合、定められた以外の色や模様を自分の好みで着用することができた。これを「一日晴装束(いちにちばれしょうぞく)」と呼んだ。色は特に季節に合わせたものだから、自分のセンスの良さを自慢する場所でもあったぞ。
そして一番上に袍を着て細かい装飾品を身につければ完成、となるわけだが思いのほか長くなったのでここで一旦終了したいと思う。何か気付いた点や間違っている点があれば遠慮なく教えてほしい。
しかし人に説明するとはかくも難しきことだと改めて痛感するものだな。
さて前回から少し間があったが、いよいよ束帯の着用順について説明したいと思う。なお細かいところを端折っている部分もあるかも知れないがそこはご容赦願いたい。
次に上半身の「小袖」だが、これが紹介されているのは「礼服」の部分で束帯のところで紹介しているものはない。手元の一冊の本に載っていたので一応描いてはみたが・・・。説明自体も多くないので何とも判断しかねるものでもあるな。
下半身の「大口袴」は裾を括っていないからその名がつき、夏冬に関係なく色はくれないと決まっていた。だから「赤大口」とも呼ばれていた。ただ若年は濃色であり、特殊な例として一日晴れの白装束の時には白を用いることもあった。
最後に「襪」だがこれは現在の靴下と同じで足袋のように親指のところで分かれていない。基本的に束帯以外の時は着用しないのが普通だった。
この単は狩衣の時などにも着用されたから、その時は束帯の時よりは多少派手になることが多かった。ちなみに今回の絵で色がオレンジぽくなっているが、これは次に着用する「衵」も同じ紅色であるから、わかりやすくするためにあえて変えたわけだ。間違えたわけではないぞ。そしてこの時足元には表袴も用意してある状態になっている。
ちなみにこれの上にさらに「半臂(はんぴ)」というものを着用していたのだが、俺たちの時代、つまり平安中期頃には冬の束帯の場合、外から見えないこともあってほとんど省略されてしまっていた。必ず着用していたのは武官の闕腋袍と、夏の縫腋袍の時だった。なのでここでの説明はさくっと省かせてもらいたい。
下半身の「表袴」だが、はっきり言って複雑な構造をしているため絵を見てもいまいち理解できかねるので(爆)説明は簡単に。
色は夏冬関係なく表が白で裏が紅。この絵だと分かりにくが裏地が少しばかり長めになっているので、裾からすこしだけ紅の生地が覗いている。つまり三枚ずれて重なっているように見えるのだが、色が似たような感じだから遠目では判断しづらい。もともとは質素なものだったが延喜以降から模様付きのものなどが登場しはじめた。模様については簡単にまとめると下記のようになる。
公卿および禁色を許された蔵人 藤丸
(若年の場合は、窠に霰(かにあられ))
老年 八藤丸
殿上人以下は模様はなく、代わりに光沢を出したりしていたぞ。
表袴は袴というよりもズボンに似たような形をしている。まあその辺りは参考資料などを見てほしい。こればかりで申し訳ない。
これが後三条天皇の時代になると大臣が七尺、大中納言が六尺、参議と散三位が五尺、四位五位が四尺というように延長され、この長さが写真などでよく見る長さとなったわけだ。大体2,3メートルくらいだな。
色目と模様はいずれの場合も表が白で、裏地は天皇が濃蘇芳、公卿殿上人は黒もしくは濃蘇芳。模様は天皇が小葵、公卿が浮線綾、殿上人はなかった(裏地もあるが省略)
そしてこの下襲は正式な儀式以外、例えば天皇の行幸など一日限りの行事などの場合、定められた以外の色や模様を自分の好みで着用することができた。これを「一日晴装束(いちにちばれしょうぞく)」と呼んだ。色は特に季節に合わせたものだから、自分のセンスの良さを自慢する場所でもあったぞ。
そして一番上に袍を着て細かい装飾品を身につければ完成、となるわけだが思いのほか長くなったのでここで一旦終了したいと思う。何か気付いた点や間違っている点があれば遠慮なく教えてほしい。
しかし人に説明するとはかくも難しきことだと改めて痛感するものだな。
改装はメールとはらお(謎)を残すのみになりました。結局平安ネタはブログでやっていくことに。いやあ楽だ(何様)とはいえ束帯しかやってないのでまた資料作りに時間がかかります。束帯の着用は明日にでも上げますので。
しかしあれですね、無双がだんだん何でもアリ状態になってきましたね(OROCHIからそうでしたが)いつからスーパーサイ○人に。源平無双はもう期待しないと言いつつ、まだどこかで淡いものを抱いてます。魔王再臨でチョイ役で出すくらいならゲーム作れよ、と思ったあたりから食指が伸びなくなりましたねぇ。
まあ出たところでムネ様がいらっさらないならスルーしますが。頼朝とセットじゃないと動かないので。遥かであからさまにムネ様がすっ飛ばされたのを見るといない確率が高いですが。
みんなもうちょっと、戦国もいいけど源平も。「好きな武将は?」て聞かれて「平宗盛」と言っても目が点になるとかそんな。ムネ様だって立派な武将ですよヘタレですけど。戦国に限って言えばメジャーすぐる信長と政宗。あと朝倉義景と蒲生氏郷と今川義元と浅井長政と明智光秀。半分くらいは「殿といっしょ」の影響。特に朝倉と蒲生。長政はムネ様を彷彿とさせるので愛。去年の仏教研修で姉川とか通過したのでむしろそこで降ろしてくれと思いました。ちなみに高速で「関ヶ原」という標識があったので必死になってカメラで押えました(笑)
そういや昨日信玄のカレシ宛てのラブレターとかテレビでやってましたが、今更(鬼)これ結構有名だと思ってたんですが。去年の風林火山が全く生かされてませんな(色々特集とかやってたわりに)
色々辛口でスミマセorz。天の邪鬼なので流行りに対して色々言いたくなるのです。そもそも自分の国の歴史が流行り廃りで乱高下するってのもどうかと思いますが。歴史=暗記っていう勉強方法もどうかと思うし。そういえば今まで歴史勉強して丸暗記とかそういうのはあんまりなかったような。歴代総理大臣は完全に暗記でした。今じゃすっかり消え去ってますが、単発で出るとまだ頭に残っているようなので出ます。松方正義とか懐かしい。「まさよし」じゃなくて「せいぎ」と呼んでました。
あれですね、教科書や参考書片手にやるよりもそれ持って現地で学習が一番効果があるような気がします。社会科見学とかそういうのにすれば?と思ったり。東京なら江戸城跡でとか。数学とかもそうかもしれないけど歴史の教え方が教師の腕の見せ所だと思います。日本史にしろ世界史にしろ。現地に行くのはなかなか難しいかもしれないけど博物館くらいになら是非行って欲しいですね。
まとまりがなくなってきたのでこれにて終了。オフ友に会ってこんな感じの話をしたいとか、そんな風に思う深夜。
しかしあれですね、無双がだんだん何でもアリ状態になってきましたね(OROCHIからそうでしたが)いつからスーパーサイ○人に。源平無双はもう期待しないと言いつつ、まだどこかで淡いものを抱いてます。魔王再臨でチョイ役で出すくらいならゲーム作れよ、と思ったあたりから食指が伸びなくなりましたねぇ。
まあ出たところでムネ様がいらっさらないならスルーしますが。頼朝とセットじゃないと動かないので。遥かであからさまにムネ様がすっ飛ばされたのを見るといない確率が高いですが。
みんなもうちょっと、戦国もいいけど源平も。「好きな武将は?」て聞かれて「平宗盛」と言っても目が点になるとかそんな。ムネ様だって立派な武将ですよヘタレですけど。戦国に限って言えばメジャーすぐる信長と政宗。あと朝倉義景と蒲生氏郷と今川義元と浅井長政と明智光秀。半分くらいは「殿といっしょ」の影響。特に朝倉と蒲生。長政はムネ様を彷彿とさせるので愛。去年の仏教研修で姉川とか通過したのでむしろそこで降ろしてくれと思いました。ちなみに高速で「関ヶ原」という標識があったので必死になってカメラで押えました(笑)
そういや昨日信玄のカレシ宛てのラブレターとかテレビでやってましたが、今更(鬼)これ結構有名だと思ってたんですが。去年の風林火山が全く生かされてませんな(色々特集とかやってたわりに)
色々辛口でスミマセorz。天の邪鬼なので流行りに対して色々言いたくなるのです。そもそも自分の国の歴史が流行り廃りで乱高下するってのもどうかと思いますが。歴史=暗記っていう勉強方法もどうかと思うし。そういえば今まで歴史勉強して丸暗記とかそういうのはあんまりなかったような。歴代総理大臣は完全に暗記でした。今じゃすっかり消え去ってますが、単発で出るとまだ頭に残っているようなので出ます。松方正義とか懐かしい。「まさよし」じゃなくて「せいぎ」と呼んでました。
あれですね、教科書や参考書片手にやるよりもそれ持って現地で学習が一番効果があるような気がします。社会科見学とかそういうのにすれば?と思ったり。東京なら江戸城跡でとか。数学とかもそうかもしれないけど歴史の教え方が教師の腕の見せ所だと思います。日本史にしろ世界史にしろ。現地に行くのはなかなか難しいかもしれないけど博物館くらいになら是非行って欲しいですね。
まとまりがなくなってきたのでこれにて終了。オフ友に会ってこんな感じの話をしたいとか、そんな風に思う深夜。
- ABOUT
しょーもない歴ヲタぶろぐ。旅行記があったり読書感想があったり。
