公任:
さて図らずも延び延びになってしまったが、ようやくこれが最後となる。ただし前回失敗したこともあるので細かくわけてそれぞれを解説したいと思う。
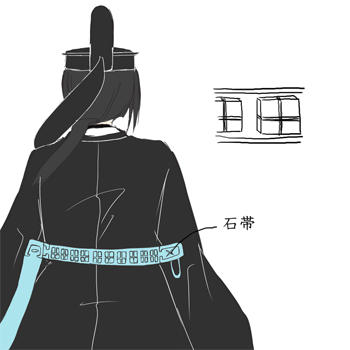
前回まで駆け足だったがとりあえず一番上の縫腋袍を着用するまでを解説したが、その縫腋袍を留めるのがこの「石帯(いしのおび/せきたい)」だ。専ら呼び方は「せきたい」のほうだから何かで調べるときはまずこちらで検索してくれ。
この石帯は分かりやすく水色で示した部分だが、要するにベルトのようなものだ。少なくとも平安時代は今と同じように一本で構成されていたようなのだが、図のように二手に分かれたのは鎌倉時代以降のことだ。ただ多くの場合、紹介されている「石帯」はこの二手に分かれているものばかりなので絵としてはこちらを採用したということを最初に述べておく。
右上の図は石帯を拡大したもので、四角いものは石帯の装飾品だ。古くは金・銀・銅だったが、平安時代はほとんど玉か石となっていて、種類としては瑪瑙や犀角(さいかく/サイの角、ただし実際は牛の角)、瑠璃、象牙などだった。加工した際の形も、このように四角いものは「巡方(ずんぽう)」と呼び、丸く加工したものは「丸鞆(まるとも)」と呼んだ。更にこれらに模様などを彫ることもあり、代表的なものをしては鬼型や獅子型、唐草などであったぞ。もちろん位階や地位によってどれを身につけてよいのか、というものもきちんと決まっていた。具体的には
無文巡方(むもんずんぽう) 天皇、帛御衣(はくのおんぞ)、または斎服の時
有文巡方(うもんずんぽう) 三位以上の厳儀の時
有文丸鞆(うもんまるとも) 公卿の通常時
無文丸鞆(むもんまるとも) 殿上人の通常時
ということになっている。天皇の帛御衣とか斎服を着ている時というのは要するに神事に際している時を指す。三位以上の厳儀とは節会や行幸の時などで、それ以外では下の二つとなるわけだ。見てのとおり、巡方のほうが厳粛な場合であるということが分かると思う。ただ石帯の中央に丸鞆、両端に巡方をつけた便宜上はどちらでも使える「通用帯(つうようたい)」というものもあったぞ。
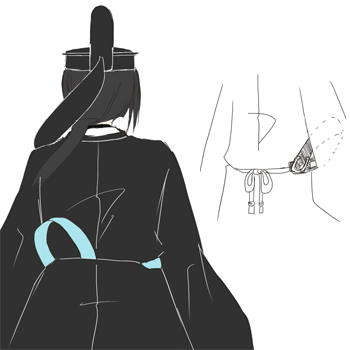
そしてこれが実際に石帯を着用した姿になる。上に反り返っている部分を「上手(うわて」、玉などの装飾品があるほうを「本帯(ほんたい)」と呼ぶ。どのように結んでいるのかといえば、右上の図のようになる。実際平安貴族の服はゆったりしたものが多く、腹部はどの服でも大体ふくらみで隠れてしまうから、そういう部分は単に紐で結ぶようなお手軽な形へと変わっていったわけだ。
次にこの石帯にかけて使う「魚袋(ぎょたい)」を紹介する。これは身に付ける儀式が決まっていて、節会、大嘗会、御禊、内宴、二宮大饗などだった。位階も五位以上となっており、素材も公卿は金、殿上人は銀として石帯の後ろの右(上手と本帯を留めてあるあたり)にかけていたぞ。形はその名の通り、魚の形をした符の袋で、
ここで言う符とは簡単に言えば通行証のようなものだ。
さてとりあえず今回はこれで終わりだ。次は飾太刀と平緒について解説するぞ。
さて図らずも延び延びになってしまったが、ようやくこれが最後となる。ただし前回失敗したこともあるので細かくわけてそれぞれを解説したいと思う。
前回まで駆け足だったがとりあえず一番上の縫腋袍を着用するまでを解説したが、その縫腋袍を留めるのがこの「石帯(いしのおび/せきたい)」だ。専ら呼び方は「せきたい」のほうだから何かで調べるときはまずこちらで検索してくれ。
この石帯は分かりやすく水色で示した部分だが、要するにベルトのようなものだ。少なくとも平安時代は今と同じように一本で構成されていたようなのだが、図のように二手に分かれたのは鎌倉時代以降のことだ。ただ多くの場合、紹介されている「石帯」はこの二手に分かれているものばかりなので絵としてはこちらを採用したということを最初に述べておく。
右上の図は石帯を拡大したもので、四角いものは石帯の装飾品だ。古くは金・銀・銅だったが、平安時代はほとんど玉か石となっていて、種類としては瑪瑙や犀角(さいかく/サイの角、ただし実際は牛の角)、瑠璃、象牙などだった。加工した際の形も、このように四角いものは「巡方(ずんぽう)」と呼び、丸く加工したものは「丸鞆(まるとも)」と呼んだ。更にこれらに模様などを彫ることもあり、代表的なものをしては鬼型や獅子型、唐草などであったぞ。もちろん位階や地位によってどれを身につけてよいのか、というものもきちんと決まっていた。具体的には
無文巡方(むもんずんぽう) 天皇、帛御衣(はくのおんぞ)、または斎服の時
有文巡方(うもんずんぽう) 三位以上の厳儀の時
有文丸鞆(うもんまるとも) 公卿の通常時
無文丸鞆(むもんまるとも) 殿上人の通常時
ということになっている。天皇の帛御衣とか斎服を着ている時というのは要するに神事に際している時を指す。三位以上の厳儀とは節会や行幸の時などで、それ以外では下の二つとなるわけだ。見てのとおり、巡方のほうが厳粛な場合であるということが分かると思う。ただ石帯の中央に丸鞆、両端に巡方をつけた便宜上はどちらでも使える「通用帯(つうようたい)」というものもあったぞ。
そしてこれが実際に石帯を着用した姿になる。上に反り返っている部分を「上手(うわて」、玉などの装飾品があるほうを「本帯(ほんたい)」と呼ぶ。どのように結んでいるのかといえば、右上の図のようになる。実際平安貴族の服はゆったりしたものが多く、腹部はどの服でも大体ふくらみで隠れてしまうから、そういう部分は単に紐で結ぶようなお手軽な形へと変わっていったわけだ。
次にこの石帯にかけて使う「魚袋(ぎょたい)」を紹介する。これは身に付ける儀式が決まっていて、節会、大嘗会、御禊、内宴、二宮大饗などだった。位階も五位以上となっており、素材も公卿は金、殿上人は銀として石帯の後ろの右(上手と本帯を留めてあるあたり)にかけていたぞ。形はその名の通り、魚の形をした符の袋で、
ここで言う符とは簡単に言えば通行証のようなものだ。
さてとりあえず今回はこれで終わりだ。次は飾太刀と平緒について解説するぞ。
PR
この記事にコメントする
- ABOUT
しょーもない歴ヲタぶろぐ。旅行記があったり読書感想があったり。
